2025年9月29日(月)から放送が始まるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ヒロイン・松野トキのモデルとなったのは、明治の文豪ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の妻、小泉セツ(1868年〜1932年)です。
ドラマでは松野トキとして描かれるセツの生涯は、まさに激動の明治日本を体現しています。士族の娘として生まれながら、時代の変化によって苦難の道を歩み、最終的には異国の文豪の魂を支える最高のパートナーとなったその波乱万丈な人生を辿ります。
もくじ
没落士族の娘、貧困と苦難の少女時代
小泉セツは慶応4年(1868年)、現在の島根県松江市で、松江藩家臣(士族)の小泉家の次女として生まれました。しかし、彼女の人生は誕生直後から試練に満ちています。
明治維新という大きな時代の変革により、武士の時代が終わり、多くの士族は禄(給料)を失い生活が困窮しました。セツの生家である小泉家も例外ではなく、直後に親類の稲垣家の養女となります。しかし、その養家もまた没落の道をたどります。
当時の松江では、士族の多くが自活の目途が立たず、極度の貧困にあえいでいました。セツは11歳という若さで小学校を中退し、家計を支えるために機織り(はたおり)の工場に出て働かざるを得ませんでした。武家の娘としての教育や気品は持ち合わせていましたが、現実の生活は過酷を極めていたのです。
最初の結婚と夫の出奔
セツは19歳になった明治19年(1886年)に婿養子を迎え、一度は結婚しますが、この結婚生活は長く続きませんでした。婿養子は松野家の深刻な借金と困窮した生活に嫌気がさし、わずか1年ほどでセツのもとを去り、他の女性と駆け落ちしてしまいます。セツは大阪まで夫を追いかけますが、説得は叶わず、失意のうちに松江へ戻ることになりました。
この苦難の時期を経て、セツは文字通り「食い詰めた」状態となり、貧しい実家(稲垣家)を支えるために、さらに過酷な選択を迫られます。その一つが、外国人のもとで働くという、当時としては世間の偏見にさらされる覚悟がいる仕事でした。
運命の出会い:ラフカディオ・ハーンとの絆
セツの人生が大きく好転したのは、明治23年(1890年)、22歳の時でした。彼女は松江に赴任してきた外国人英語教師、ラフカディオ・ハーンの家で住み込みの女中として働くことになります。
ハーンはギリシャ生まれのアイルランド人(後に英国籍、小泉八雲として日本に帰化)。世界を転々とし、最終的に日本という異国の地に安住の地を求めてやってきた人物でした。彼は風邪をこじらせて寝込んでしまい、その身の回りの世話をするためにセツが紹介されたのが、二人の運命的な出会いとなりました。
二人は当初、言葉や文化の違いに苦労しますが、やがてお互いの心に通じるものを見出します。ハーンは、セツの持つ日本の古い文化や風習に対する深い愛情と、彼女が語る怪談や古民話に強く魅了されました。
セツが語る話は、ハーンにとって創作の源泉でした。それは単なる伝説ではなく、時代の波の中で忘れ去られ、埋もれていった名もなき人々の喜びや悲しみ、すなわち「心の物語」だったのです。セツは、ハーンという「西洋の眼差し」を通して、自らの故郷の文化や人々の心情を世界に伝えるという、新たな生きる意味を見出しました。
文豪の魂を支えた最高のパートナーへ
出会いから間もない明治24年(1891年)、セツはハーンと国際結婚します。当時、外国人との結婚は非常に珍しく、周囲の驚きや偏見も大きかったと言われています。
ハーンはセツと結婚した後、日本に帰化して小泉八雲と名乗り、日本研究家・随筆家としての名声を確立しました。セツは八雲の文学活動において、再話文学の「語り手」として不可欠な存在となります。彼女の豊かな知識と記憶力が、八雲の代表作となる『知られぬ日本の面影』や『怪談』の執筆に大きく寄与しました。
八雲は後年、セツとの松江での生活を「人生で最も幸せな時だった」と回想しています。セツは、激動の時代に故郷をさまよった八雲に、「家庭」という心の安らぎと、「古き良き日本」という創作の源泉を与えた、まさに最高の伴侶だったのです。
没落士族の娘から、世界的な文豪の妻へ。「ばけばけ」というタイトルが象徴するように、時代の流れと個人の意志によってその役割を「化けさせて」いった小泉セツの波乱に満ちた生涯は、私たちに深い感動と勇気を与えてくれるでしょう。髙石あかりさんが、この愛と絆の物語をどう演じきるのか、放送が待たれます。
次の記事も人気です。ぜひご覧になってくださいね。

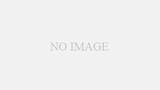
コメント