2025年9月29日(月)に放送が始まるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。
主演・髙石あかりさん演じるヒロイン・松野トキ(モデル:小泉セツ)と、トミー・バストウさん演じる夫・ヘブン(モデル:ラフカディオ・ハーン/小泉八雲)の夫婦の物語は、単なるラブストーリーではありません。それは、激動の明治時代に、国境と文化を超えて「怪談」というフィルターを通して、日本の「心模様」を世界に伝えた二人の愛と共同作業の記録です。
本作の物語の核となる「怪談」とは、一体何だったのか。そして、なぜこの夫婦が世界的な文豪を生み出すことになったのか。その深層に迫ります。
もくじ
「うらめしい」時代に埋もれた声
物語の舞台となる明治時代は、西洋文明が雪崩のように流れ込み、日本が劇的に近代化を果たした時代です。しかし、その急速な変化の裏側には、多くの「うらめしい」現実が横たわっていました。
ヒロイン・トキは、没落した士族の娘として極貧生活を送り、社会の厳しい現実と偏見にさらされてきました。彼女の周りには、時代の波についていけず、忘れ去られた人々がたくさんいます。古い習慣や信仰、そして彼らの心に残る切実な思いや悲哀は、新しい時代において「非科学的」「古臭い」ものとして、次々と切り捨てられていきました。
トキが幼い頃から愛してやまない「怪しい話(ばけもの)」、すなわち「怪談」は、まさにこの時代に居場所を失った人々の声の結晶でした。それは、人が持つ喜び、悲しみ、怒り、そして愛といった、理性では割り切れない深い感情が、形を変えて語り継がれてきた物語だったのです。トキは、その怪談に心を寄せ続けることで、時代の影に生きる人々の孤独を理解し、彼らの「心模様」を唯一知る人物となります。
怪談が結んだ、国境を越えた「愛の交換」
そんなトキの運命を変えたのが、異国から松江にやってきた英語教師のヘブンでした。彼は、故郷を失い、世界中を旅して安住の地を探し求める「さまよえる魂」を持つ人物。日本文化を研究する彼は、トキが語る怪談に、西洋の合理主義とは異なる、日本の深い精神性を見出しました。
当初、言葉や文化の違いに戸惑い、苦労した二人ですが、「怪しい話好き」という共通点で心は深く通じ合います。そして、彼らの関係は単なる恋愛を超え、「共創」の形へと発展していきます。
トキは、自分が松江で見てきた、あるいは古老から聞き継いだ怪談、民話、そして市井の人々の暮らしの物語を、飾り気のない日本語でヘブンに語ります。ヘブンは、その素朴で情感豊かな「語り」を、英語で記録し、再構成します。
これは、文豪ラフカディオ・ハーンの傑作『怪談』が生まれたプロセスそのものです。セツ(トキ)が「心」を語り、ハーン(ヘブン)がそれを「言葉」にする。この夫婦による共同作業によって、近代化の中で日本人が見失いかけていた「怪談」の持つ美しさや切なさが、初めて普遍的な物語として世界に翻訳され、伝えられることになったのです。
「ばけばけ」に込められた、心模様の力
本作のタイトル**『ばけばけ』**には、「化ける」という意味が込められています。
-
物語が「化ける」:単なるおどろおどろしい話が、普遍的な人々の「心模様」へと昇華する。
-
トキが「化ける」:貧しい一介の娘が、世界的な文豪の創作活動を支える「語り手」へと変貌する。
二人の愛の軌跡は、まさに「言葉や文化が違っても、人間の心は通じ合える」という希望のメッセージです。トキが語り継いだ日本の「心模様」は、ヘブンという異文化の視点を通すことで、世界中の読者の魂に深く響く文学へと「化けた」のです。
「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」
このキャッチコピーが示すように、『ばけばけ』は、人生の苦難(うらめしさ)の中にこそ、愛する人との絆や、人々の心に残る物語(すばらしさ)があることを教えてくれます。
髙石あかりさんとトミー・バストウさんが演じる、この異色の夫婦が、明治という激しい時代にどんな「心模様」を紡ぎ、世界へと伝えたのか。その感動的な日々を、ぜひ毎朝見届けてください。
次の記事も人気です。ぜひご覧になってくださいね。

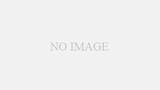
コメント